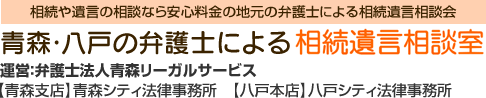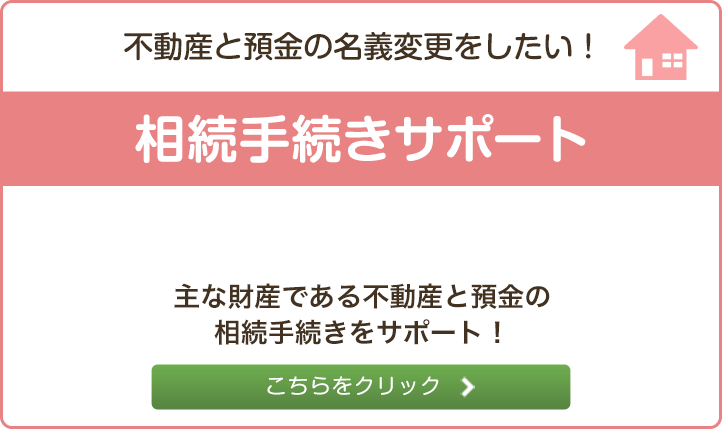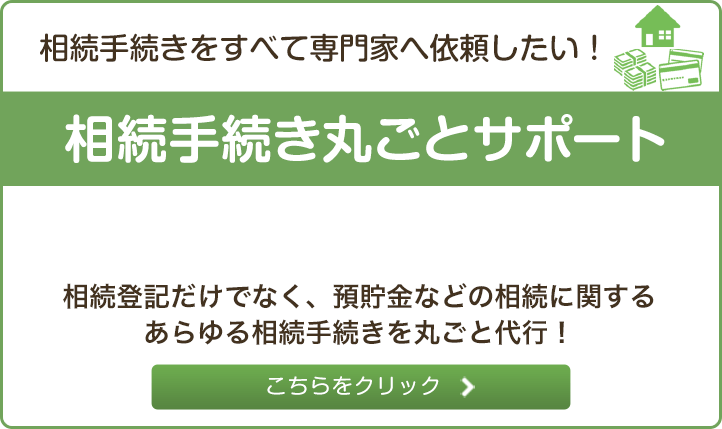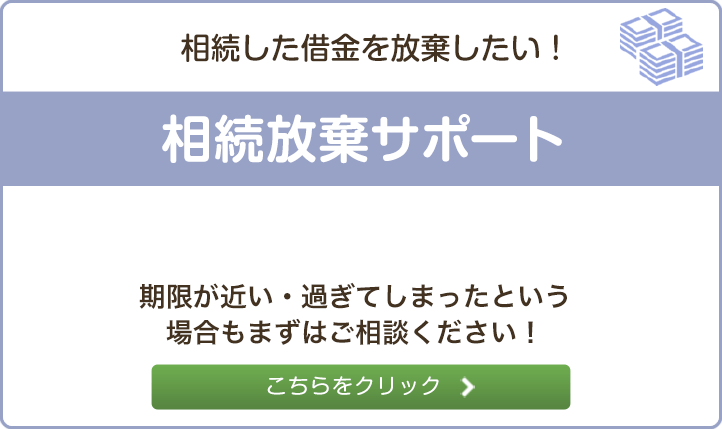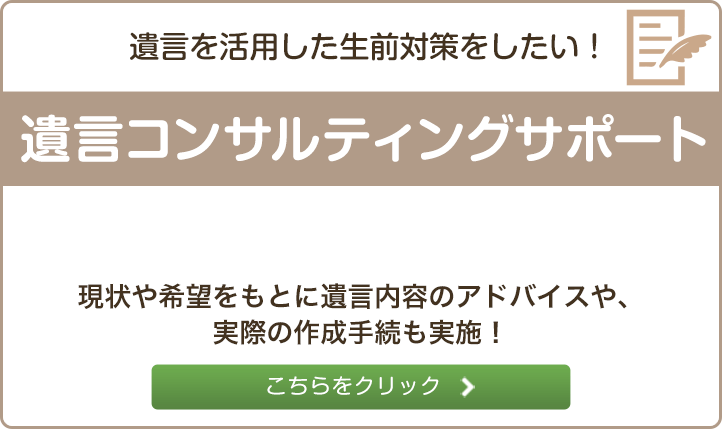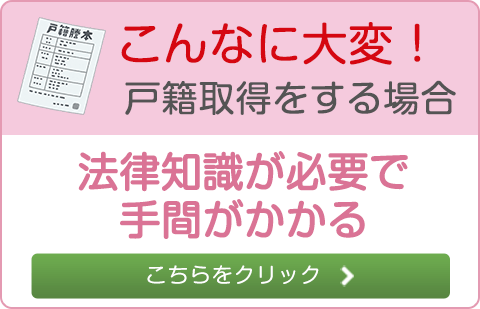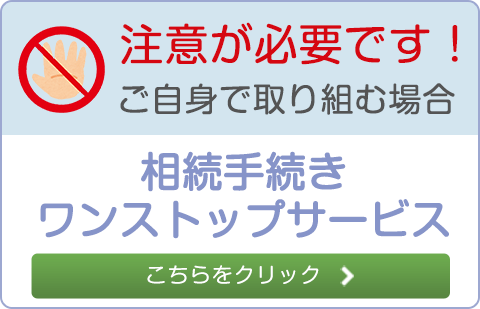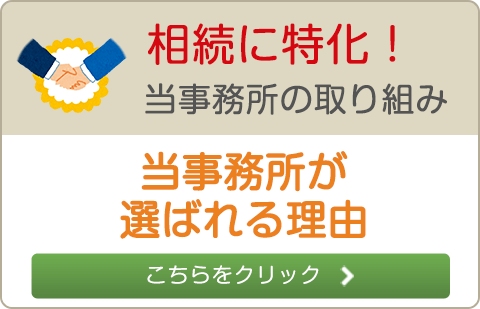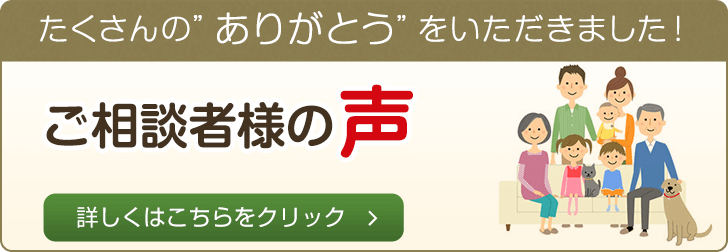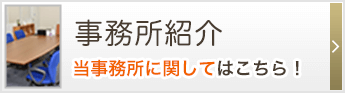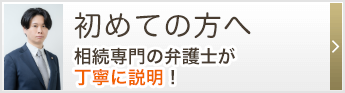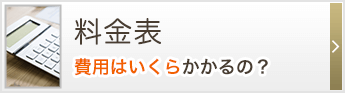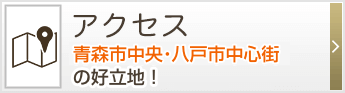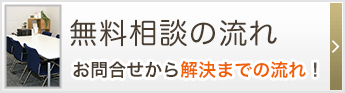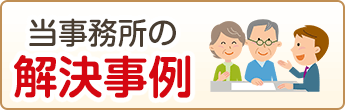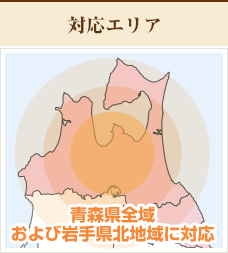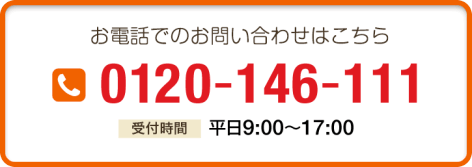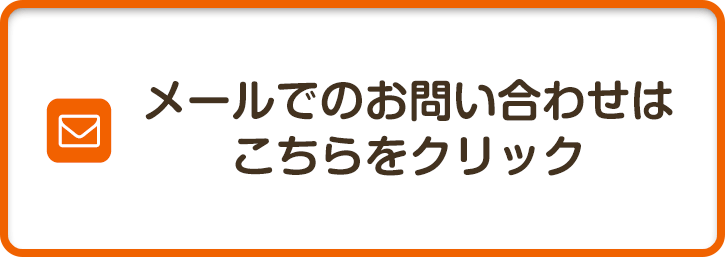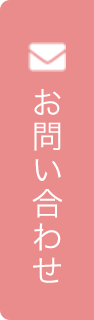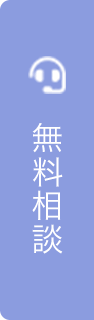外国人が亡くなった場合、相続の手続はどうなる?
1 どこの国の法律が適用される?
日本に居住している外国人が亡くなった場合、相続の問題を判断するにあたって、まず初めにどこの国の法律が適用されるかを明らかにする必要があります。
この適用される法律のことを「準拠法」と言います。
準拠法は、「法の適用に関する通則法」という法律で定められており、そこでは「相続は、被相続人の本国法による。」と定められています。
したがって、外国人が亡くなった場合の準拠法は、原則として、その外国人が国籍を有する国の法律が適用されることになります。
ただし、亡くなった外国人が日本と他の国の二重国籍を有している場合や、亡くなった外国人に国籍がなく長年日本に居住している場合には、例外的に、日本の法律が適用されることになります。
また、国によっては、準拠法を不動産の所在地の法律とする、と定めているところもあるため、この場合、日本に所在する不動産の相続に関する準拠法は日本の法律となります。
2 相続財産に日本の不動産が含まれている場合の手続
以上のように、準拠法がどこの国の法律となるかが決まると、その準拠法に従って相続人の範囲や相続分などの相続の問題を解決することができます。
その結果、日本に所在する不動産を相続することになった場合には、日本の法務局で相続登記を行う必要があります。
そして、法の適用に関する通則法では、不動産の登記にかかる準拠法は、不動産の所在地の法律とすると定められています。
したがって、日本に所在する不動産を相続した場合には、日本の不動産登記法の手続きに従って相続登記をしなければなりません。
そして、実際に不動産の相続登記を申請するにあたっては、不動産を取得した者が被相続人の相続人であることを示す書類が必要になります。
被相続人が日本人の場合、被相続人や相続人の戸籍謄本などの書類を提出することで相続関係を証明することができますが、多くの国では戸籍制度が存在しません。
そのため、そのような国の場合には、戸籍に代わる証明書として、
・出生証明書
・婚姻証明書
・死亡証明書
といった書類を被相続人の本国から取得する必要があります。
ただし、実際には、上記の証明書だけでは、相続人の範囲がわからないため、これらの証明書のほかに、相続人全員が在日領事館や公証役場で「被相続人の相続人は自分たちのみであり、そのほかに相続人は存在しません。」という宣誓をした内容をまとめた宣誓証明書を作成し、これを提出することになります。
なお、これらの証明書は、通常、外国語で作成されるため、法務局に申請するには、日本語訳を添付する必要があります。
3 被相続人が外国人の場合の相続税
(1) 課税対象
相続税の課税対象は、基本的には、相続人や被相続人の住所と財産の所在地によって決まります。
まず、相続人が日本国籍を有しており、日本に居住している場合には、被相続人が外国人であったとしても、原則として、国内財産・外国財産を問わず、すべての財産が日本の相続税の課税対象となります。
他方で、相続人が日本国籍を有しているものの、外国に居住している場合には、国内財産のみが日本の相続税の課税対象となります。
ただし、相続人が外国に居住しているとはいっても、被相続人死亡前10年以内に日本に住民票をおいていた場合には、原則どおり、すべての財産が日本の相続税の課税対象となります。
また、相続人が外国に居住し、被相続人死亡前10年以内に日本に住民票を置いていなかったとしても、被相続人が外国人であり、その住所が日本にあった場合には、同様に、すべての財産が日本の相続税の課税対象となります。
(2) 相続税の計算
日本における相続税の計算方法は、基本的には、法定相続人が法定相続分に従って遺産分割を行ったと仮定した場合を前提に算出されます。
そして、日本に対して支払う相続税である以上、その際に考慮される法定相続人の範囲や法定相続分の割合は、被相続人が外国人であったとしても、日本の民法の規定によって判断されます。
なお、前述のとおり、相続における準拠法は被相続人の本国法が適用されるため、本国法における法定相続人の範囲や法定相続分が、相続税の判断にあたって前提とされた日本の民法の規定における法定相続人の範囲や法定相続分との間に差異が生じる場合があり得ます。
もっとも、相続税は実際に相続する人に課せられるものであるため、相続税の算出にあたって日本の民法の規定を前提としても、準拠法の適用の結果、相続人ではなかったり法定相続分が違う相続人が生じたりした場合にも、そのまま相続税を課すと不都合が生じます。
そのため、このような場合には、算出された相続税は、実際に相続で適用された準拠法による法定相続分に基づいて各相続人に割り当てられることになります。
(3) 相続税の申請期限
相続税は、被相続人の死亡を知ってから10か月以内に申請・納税をしなければなりません。
もっとも、外国人が相続人の場合、前記のように、被相続人の本国法の規定を調査することはもちろんのこと、被相続人の外国に所在する財産も調査しなければならないことから、期限に間に合わないことが多々あります。
このような場合には、実際の遺産分割に先立ち、法定相続分に従って財産を相続したと仮定した場合に発生する相続税を申告・納税する「未分割申請」という方法を用いることができます。
この場合、その後に遺産分割が成立し、実際に取得した財産と法定相続分との間で過不足が発生した場合には、修正申告や更生請求を行うことで調整することが可能です。
4 日本の不動産の相続登記の手続
外国人が被相続人であったとしても、基本的には、日本人が被相続人の場合における不動産の相続登記をする際の流れは変わりません。
(1) 遺言書の確認
まずは、遺言書の有無を確認する必要があります。
不動産に関する遺言書の形式は、
・遺言書を作成した国
・遺言書を作成または死亡した当時に国籍を有した国
・遺言書を作成または死亡した当時に住所を有した国
・遺言書を作成または死亡した当時に常居所を有した国
・不動産が所在する国
のいずれか法律の形式に適合していれば、有効とされています。
したがって、日本では認められていない方法・形式での遺言書が見つかる可能性があるため、十分に調査をする必要があります。
(2) 準拠法の調査
前述のとおり、被相続人が外国人だからといって、必ずしも、外国の法律が適用されることになるとは限りません。
被相続人の本国法を確認し、準拠法が日本法となる余地がないかを調査する必要があります。
(3) 相続人調査・相続財産調査
準拠法に従って、法定相続人を調査する必要があります。
被相続人が戸籍制度のある国の国籍を有する場合には、戸籍を取得すれば十分ですが、前述のとおり、戸籍制度がない国の場合には、調査や取得しなければならない書類が多岐にわたります。
また、これと同時に、相続財産を調査する必要があります。
もっとも、外国に資産を有する場合、国によっては被相続人の死亡と同時に遺産が凍結される制度が採用されているところもあります。
そのため、相続財産を一部切り崩して相続税に充てるという方法が取れない可能性があります。
このようなことから、相続税の納税期限に間に合わない可能性があるため、被相続人の生前から財産の調査をしたり相続対策をしたりすることを念頭に入れておく必要があるでしょう。
(4) 遺産分割
以上の調査を経た後、実際にどのように遺産を分配するのかを決めることになります。
相続登記を行うためには、遺産分割協議書を作成し、これに実印による押印をした上で、印鑑登録証明書を添付する必要があります。
もっとも、日本に住民票がない相続人には、登録している実印が存在しないため、印鑑登録証明書を作成することができません。
このような場合には、印鑑登録証明書の代わりに、領事館などの在外公館で署名証明書を作成し、これを添付することになります。
なお、遺産分割調停など裁判所の手続きを用いて遺産分割が決まった場合には、印鑑登録証明書は不要なため、署名証明書も不要となります。
(5) 法務局への申請
遺産分割が完了したら、必要書類を法務局に申請する点は、被相続人が日本人の場合と変わりません。
前述のとおり、被相続人が外国人の場合には、戸籍の代わりに、出生証明書、婚姻証明書などの書類を準備する必要があります。
(弁護士・下山慧)